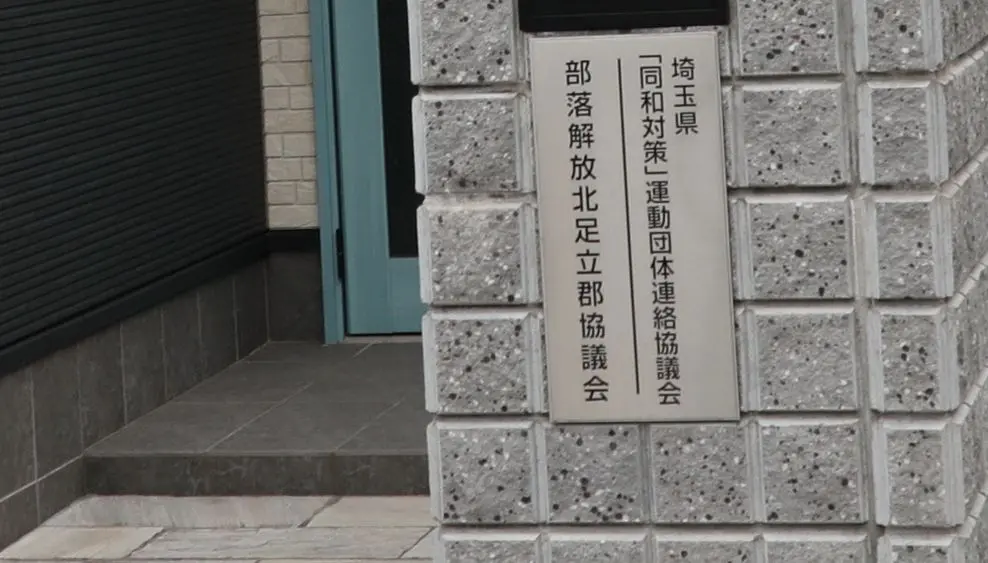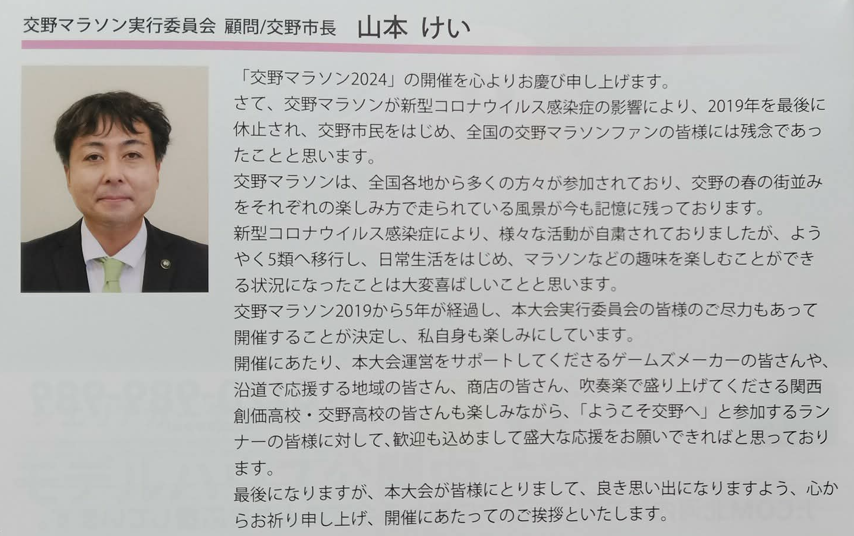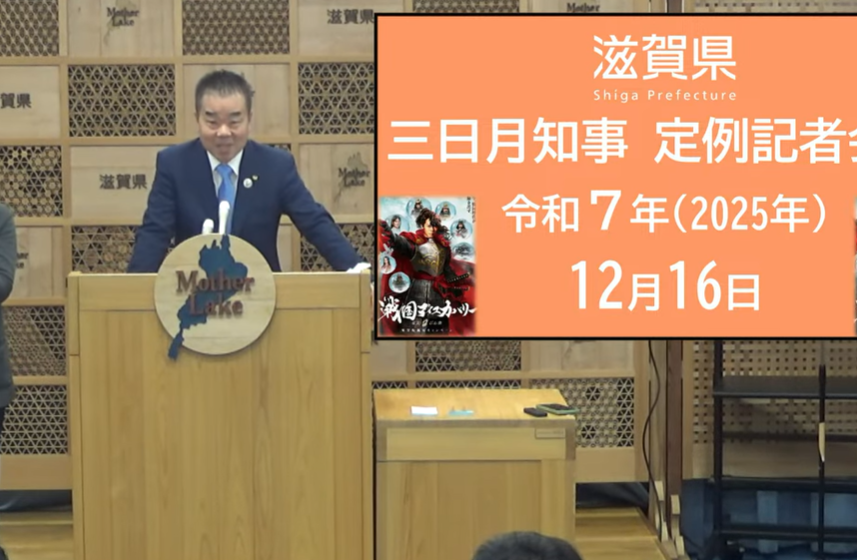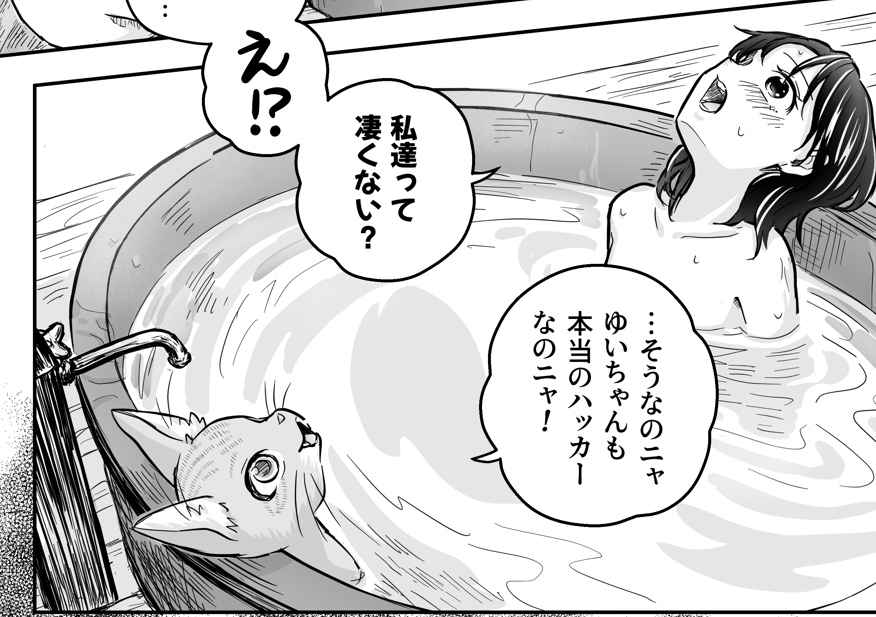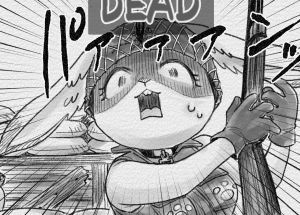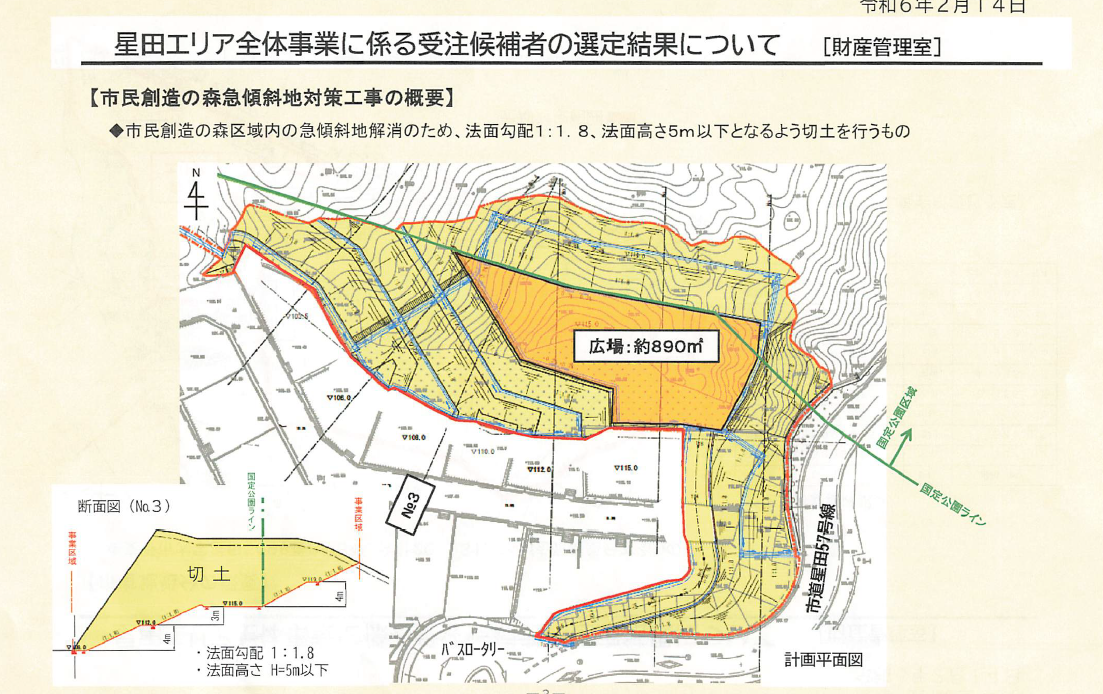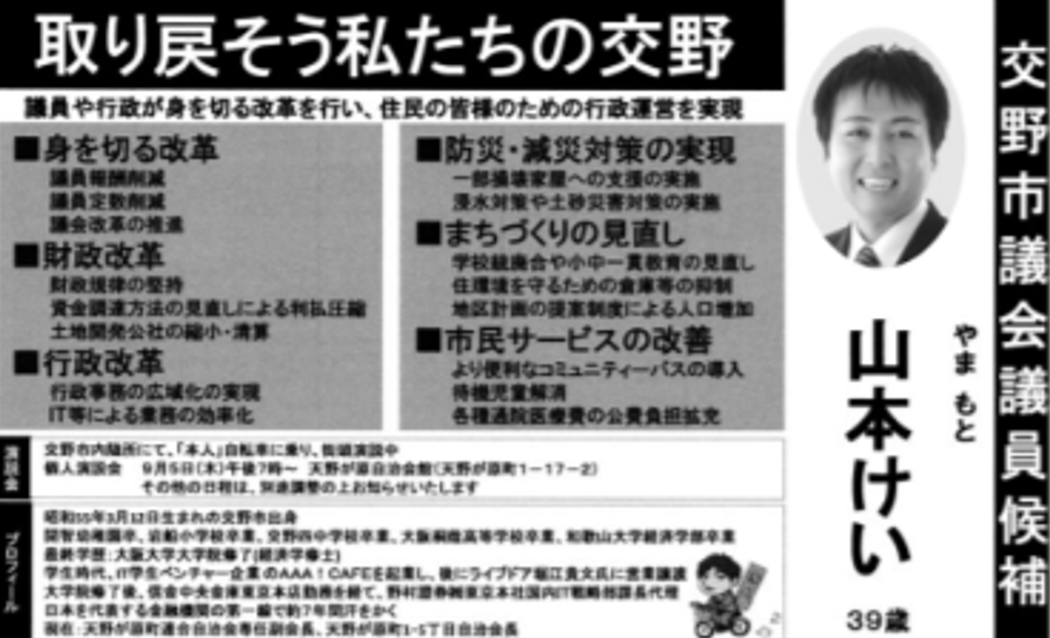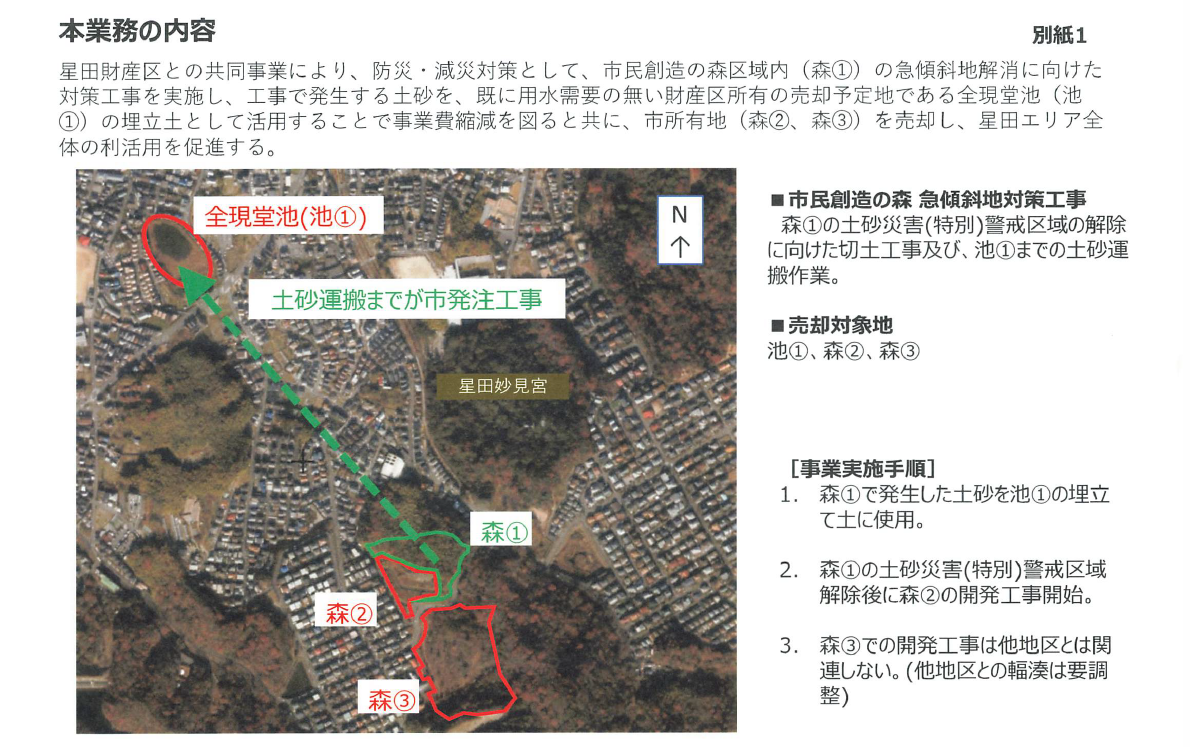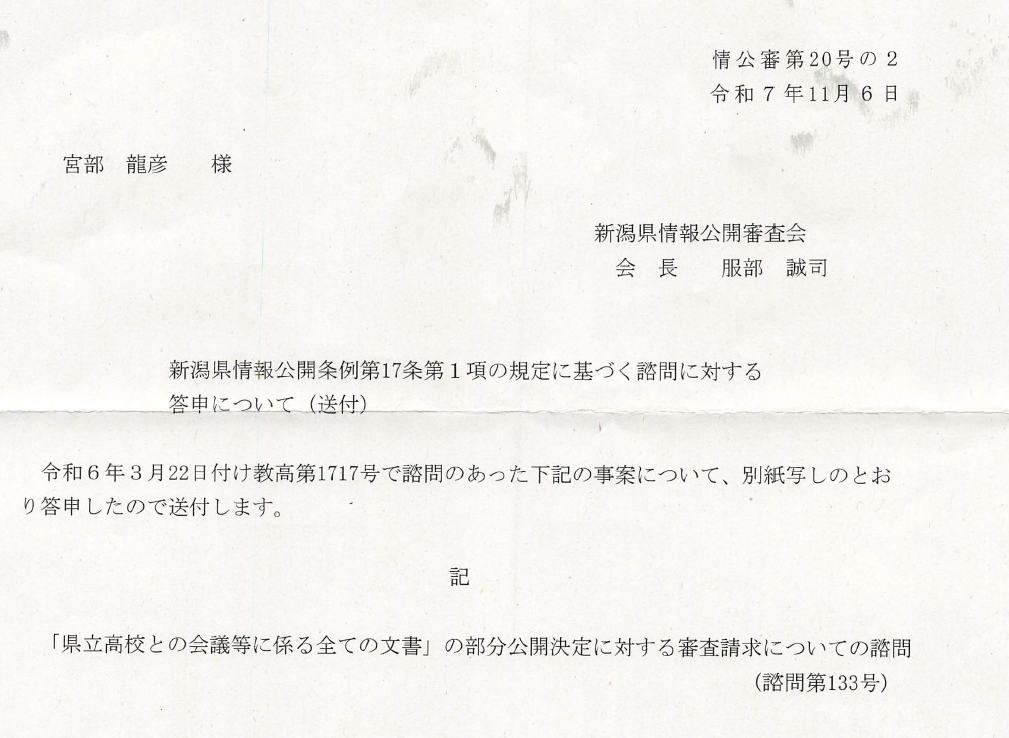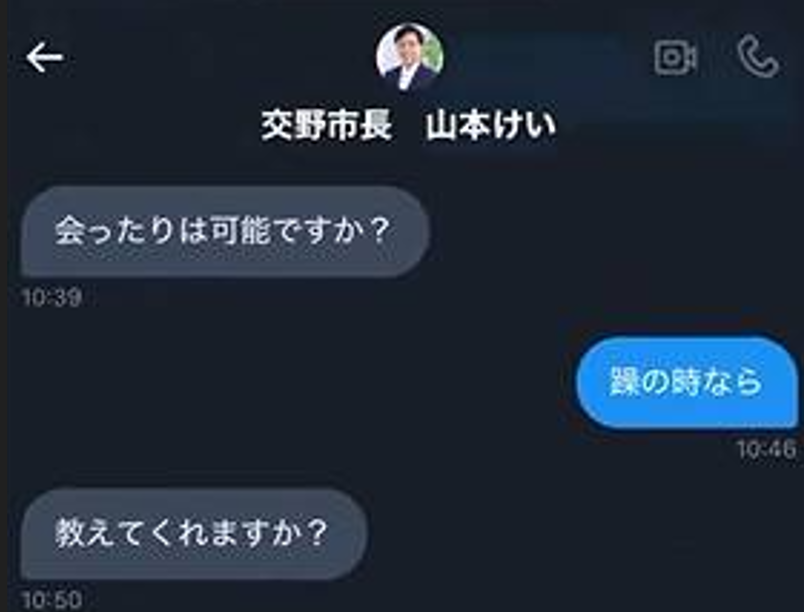津市の旧安濃町に生水という古村があるが、ここについては謎が多い。
分かっているのは、旧安濃町は同和事業をしなかったということだ。同じ安濃郡の雲林院とは対照的である。旧安濃町には2つの古村があるが、いずれも同和地区指定はされていない。

まず目についたのは生水公民館。同和施設ではないが、その作りや佇まいは他の同和施設に似ているところがある。

人権尊重都市のポスターがあるが、これは津市では一般の施設にもあるものだ。「ヘイトスピーチ、許さない」のような法務省人権擁護局の掲示物がないので、ここはやはり同和施設ではないのだろう。


ただ、未指定地区であっても生水のことは、津市内では知っている人は知っている程度に知られているという。
そのため、ただでさえ偏見を持たれているのだから「やっぱり部落の者は」と言われることがないように、決して恥ずかしい振る舞いをしてはいけないと親から強く言われてきたと、ある住民は語った。

明治初期の記録である『三重県部落史料集(近代篇)』の「壬申戸籍調査集計表」には安濃郡安部村11戸との記載がある。そして、明治期の地図には「安部清水」と記載されている。

これが昭和初期の「管内◯◯部落と其人口 」には草生村生水26戸と記載が変わっている。

ある住民によれば、確かに昔は安部村だったという。それがいつしか、草生村の所属になったのだ。住民によれば、昔を知る人がどんどん亡くなってしまったので、詳しい経緯は分からないという。

ただ、村の起こりについては、何かの戦で落ち延びてきた人々であると伝承されているそうだ。

「壬申戸籍調査集計表」によれば、檀那寺は亀山市の法善寺だが、今は寺替えしているという。

『三重県部落史料集』にもほとんど記述がなく、水平社運動があった様子もない。一貫して寝た子を起こさない方針であったのだろう。


他の安濃郡の古村にも共通することだが、農業が主である。生活程度は悪くなかったようである。

この古村については、特に悪い評判は聞かない。不思議と人を笑顔にする古村ではないだろうか。