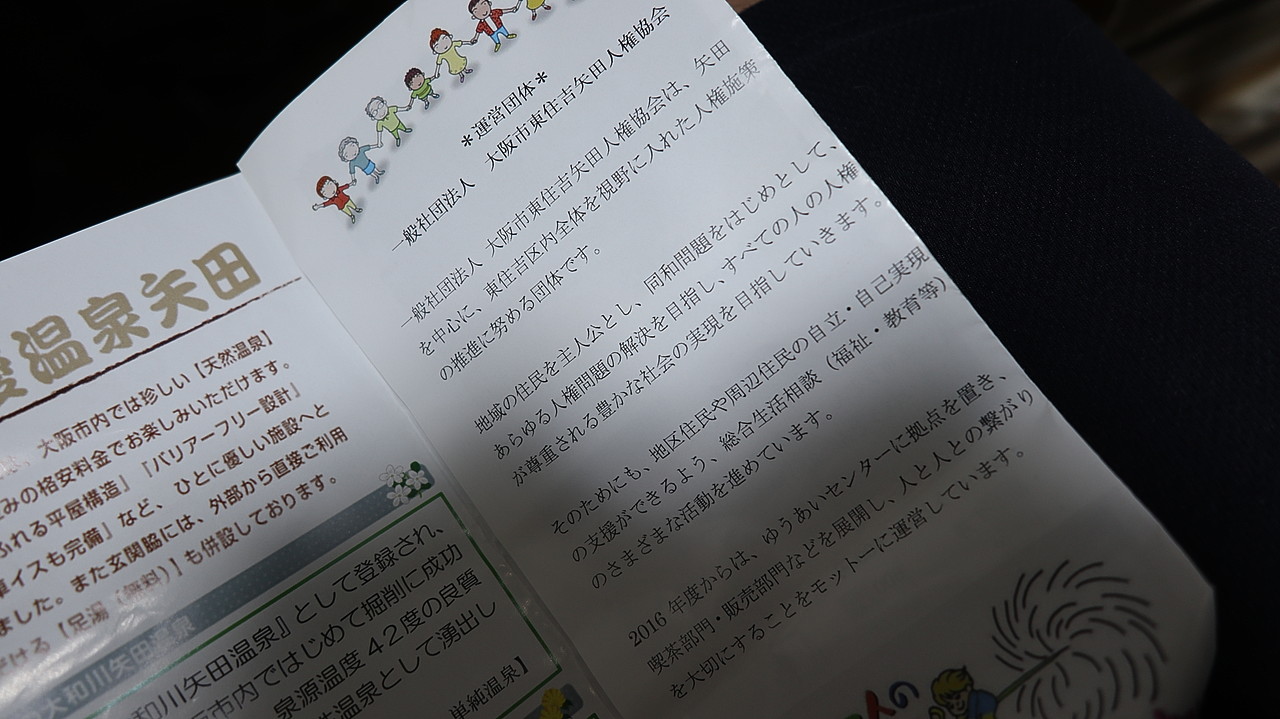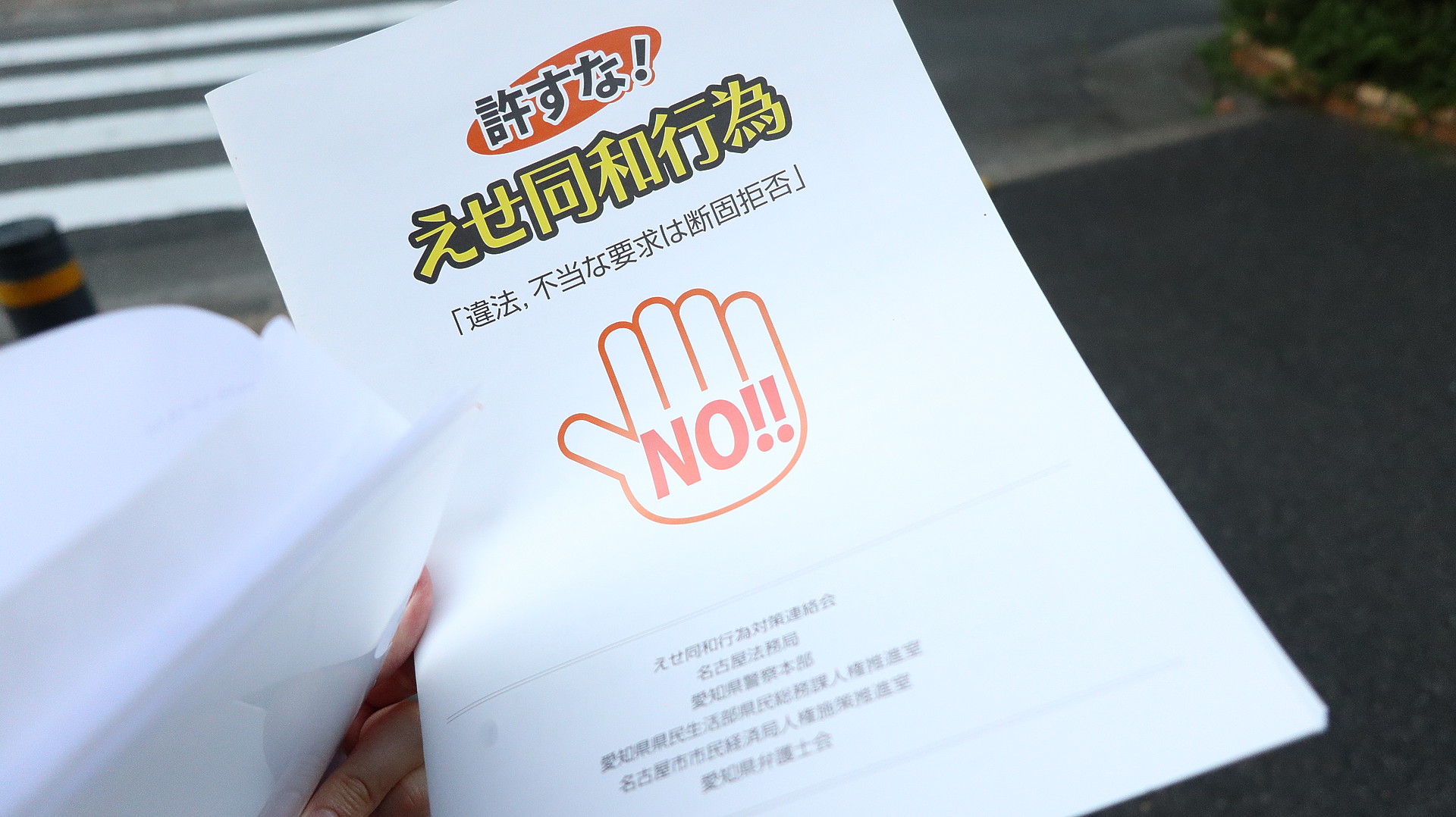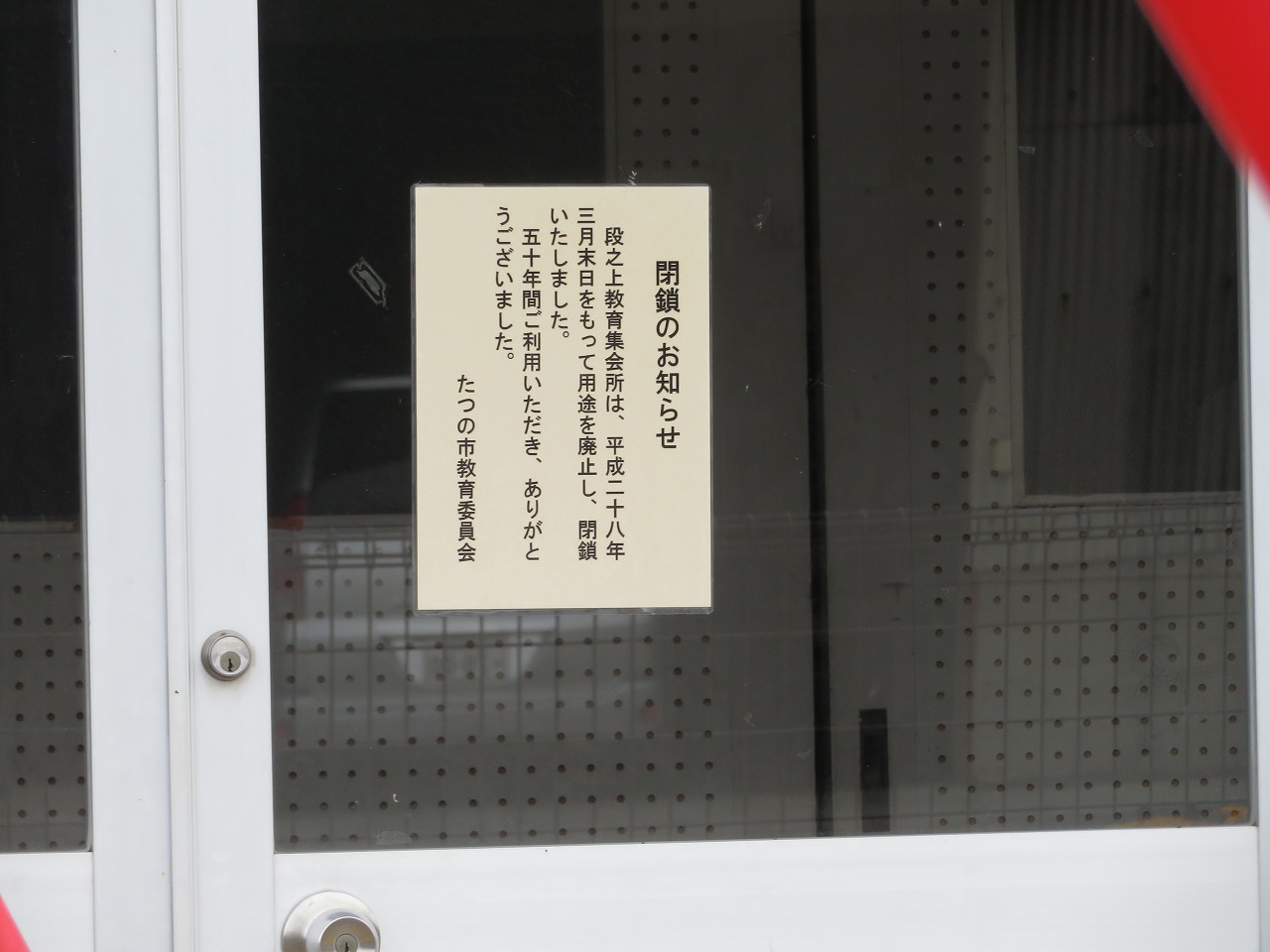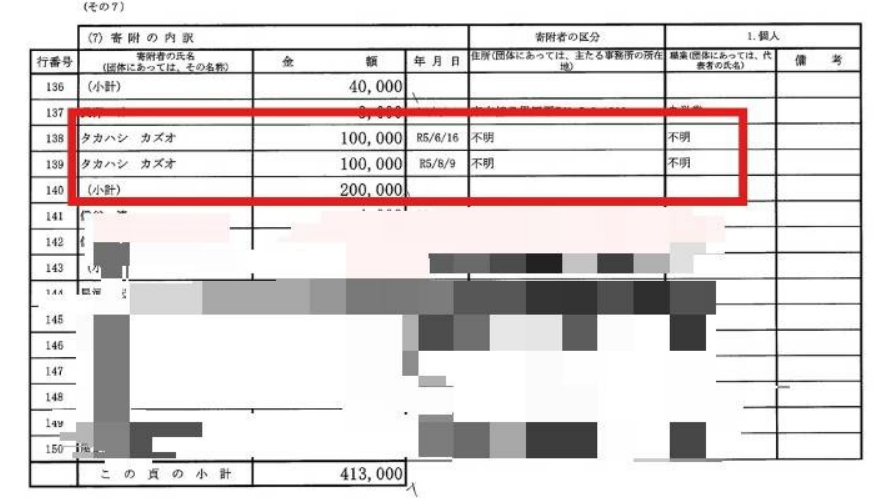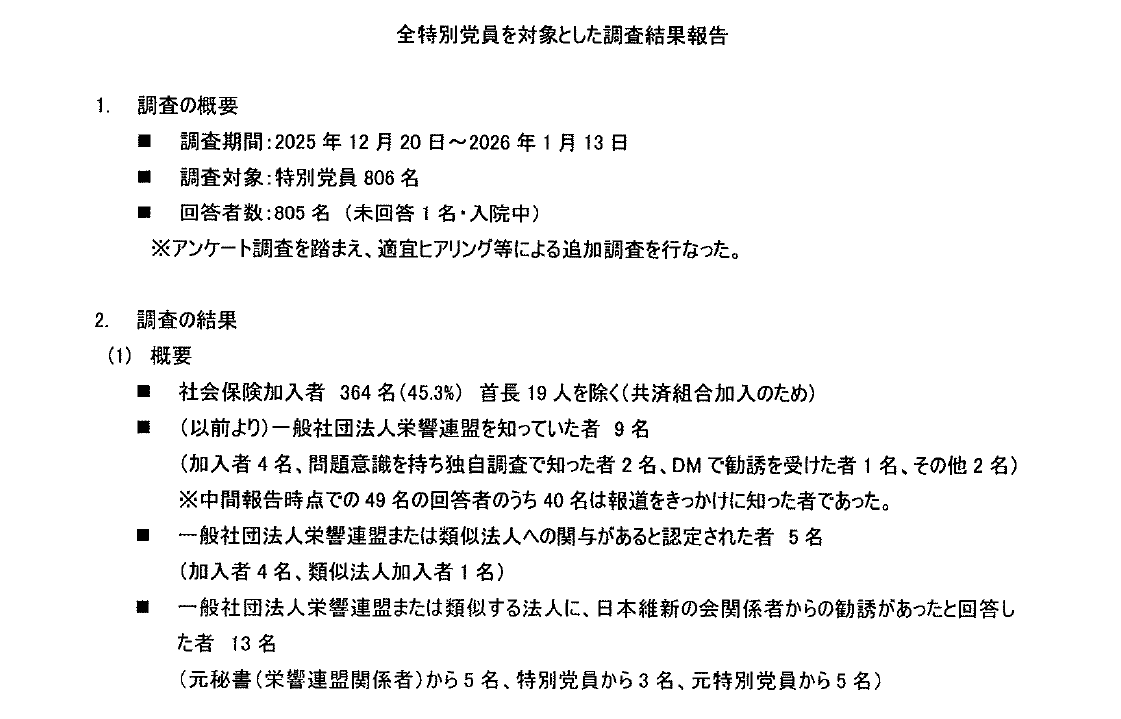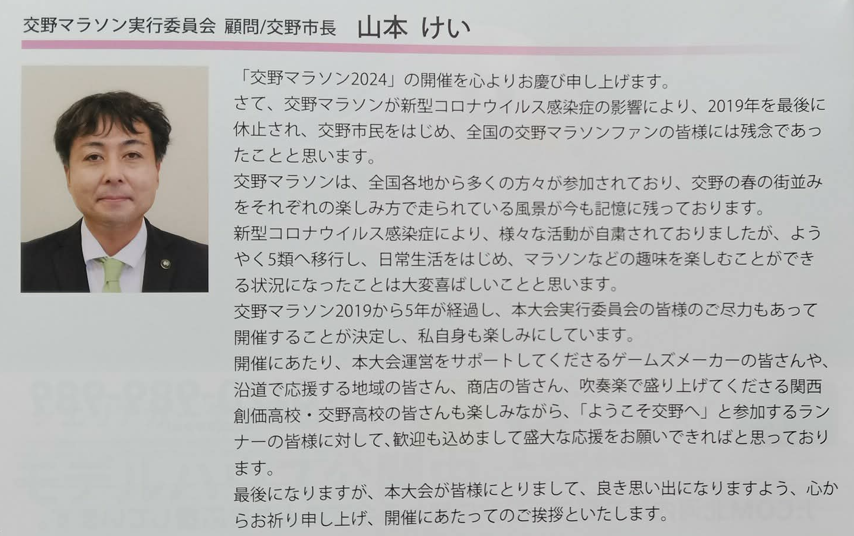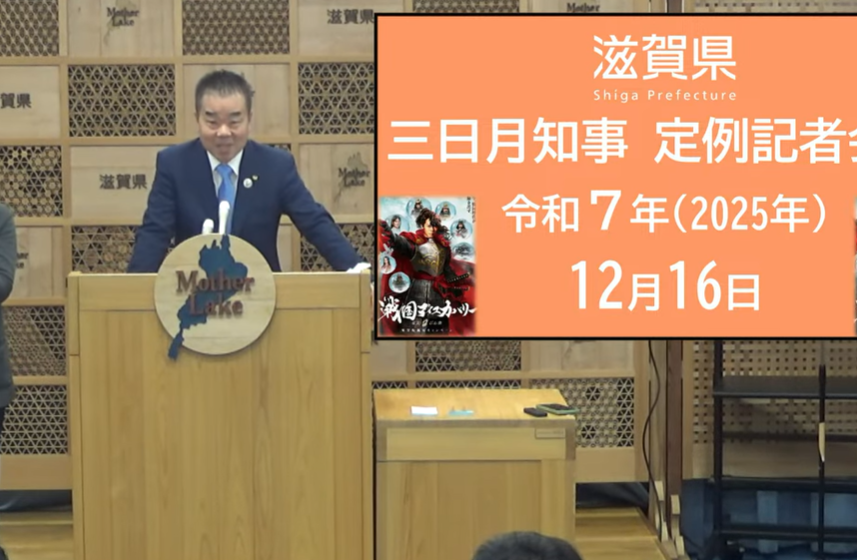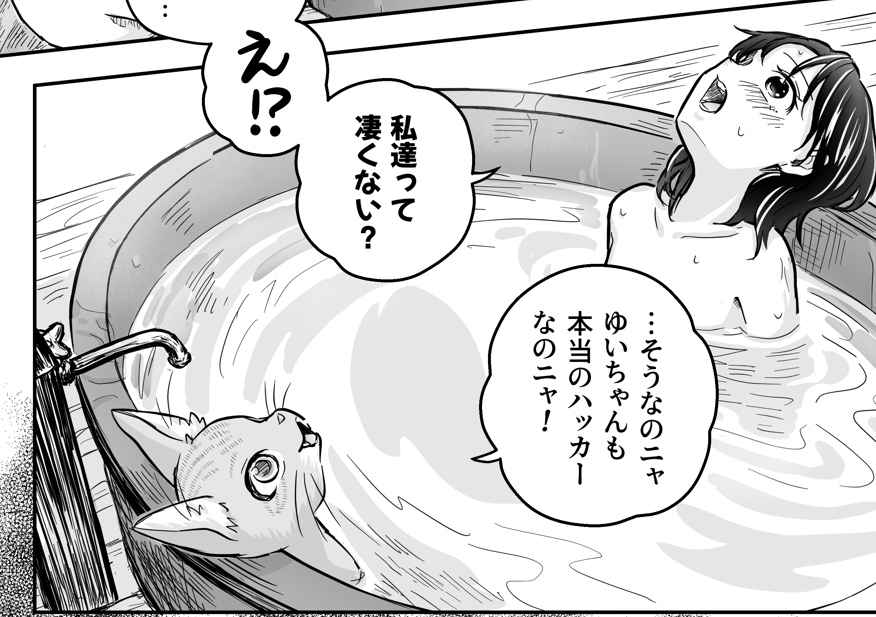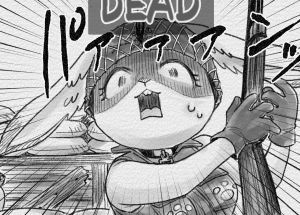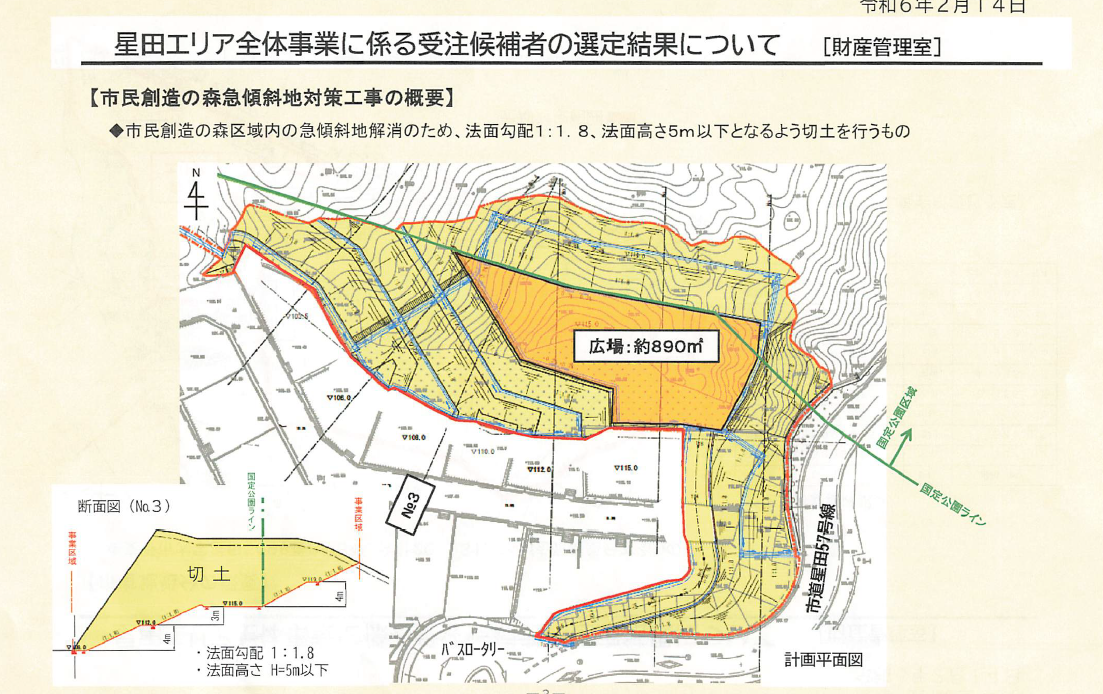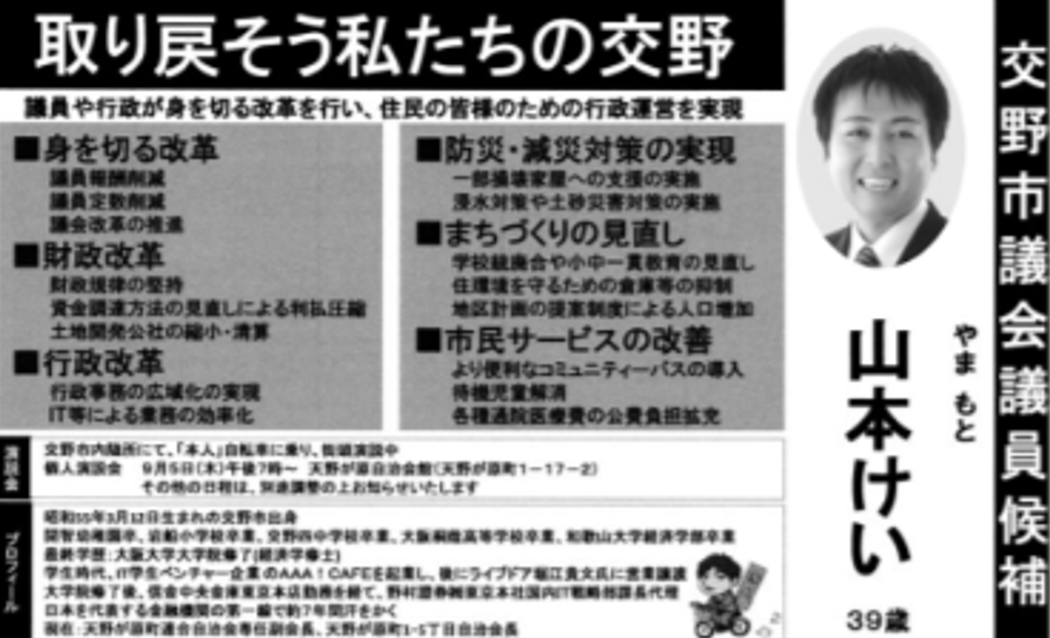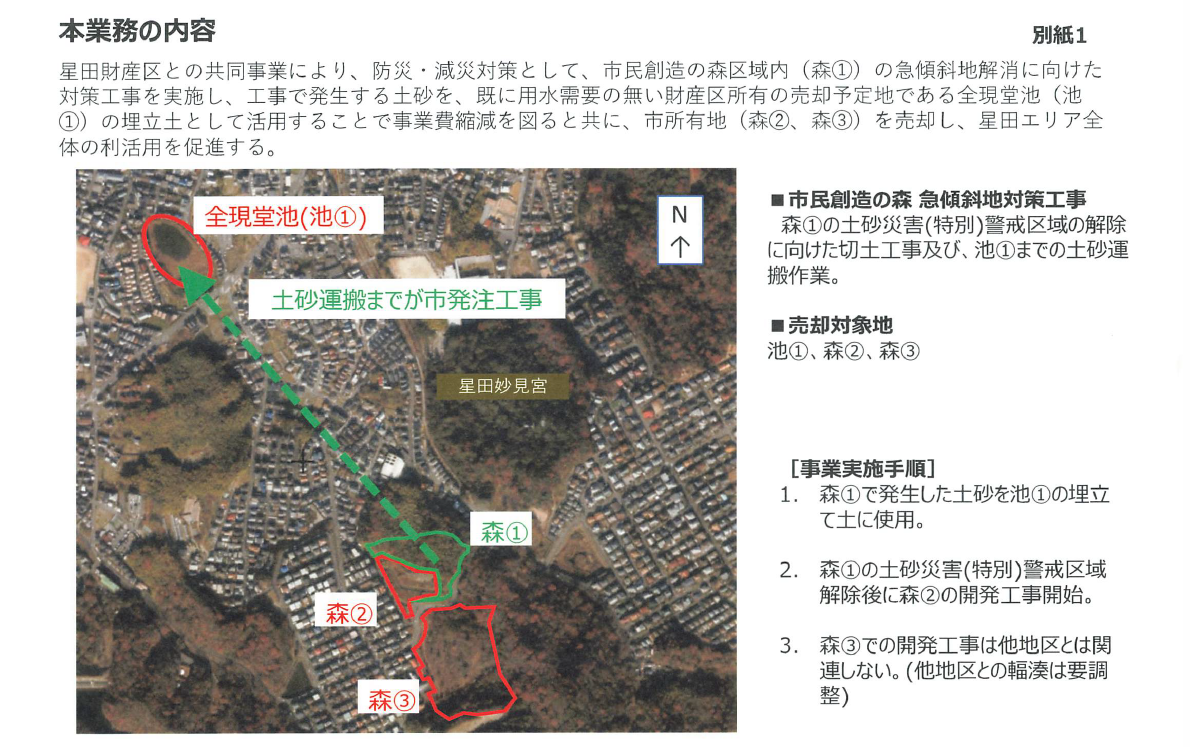「北本デジタルアーカイブス」にある『北本市史』によると、昭和48年に同和対策集会所として堀の内集会所が建設されたという。その場所は北本市石戸宿3丁目である。
石戸宿は昭和8年に中央融和事業協会による「経済更生指定地区」に指定されている。


これがその同和対策集会所。市史に掲載されウェブでも公開されているのだから、アウティングではない。

昭和10年の記録では49戸、農業が主で他に工業、商業。経済更生事業として農産物の共同販売、醤油の自家醸造、養豚に着手していたという。

菊池山哉は特に詳細に記録している。
北足立郡、石戸村、堀之内
○川越から鴻之巣、又は桶川へ赴く街道筋に位する。今は僻遠の地である。
○白山神、樹木の繁る、境内をもち、また長い参道もあり、鎭守として一般村のものに勝るとも劣らない。且つ奥の院と称する宮社もあり、杉木立の奥深く、丘上に鎭座して居る。
○農家五十戸許り。昔から堀之内村として、全村曲輪である。藁細工はして居るが、何れも大きな農家である。

確かに長い参道がある。

佇まいはまさに菊池山哉が書いたとおりだが、神社の名前が違っている。

しかし、かつては白山神社であったことが由緒書きに明示されている。



○この曲輪には
東光寺
なる寺がある。その境内には、貞水二年の国宝板碑があり、関東板碑の始源として、斯界に其名は高く、且つ同所にある蒲桜は、天然紀念物として政府から保護されて居るので、旁々特記されねばならない。

○「風土記稿」は,石戸宿を石戸の本村と見て居るが、宿は近頃のもので、村が先きである。石戸村の生じた宿であるから、石戸宿と構へるので、本村は下石戸村方面と見るべきものである。
石戸領二十ケ村一帯は、先づ曠野と見るべきもので、続く桶川宿あたり十ヶ村を、伊奈ノ庄と唱へる。この方が古い村々で此辺の古郷名を伊奈尾ノ郷と云。この郷に生じた庄園が,伊奈ノ庄である。○又「同書」に「土人の伝ヘに、村内小名堀之内とは、往古石戸左衛門尉の住せし地なりと」とあるが、これは堀之内の文字名に拘泥したもので、曲輪である以上、館址などあるべき筈はない。
且つ土塁そのものも、堀之内を擁護したものでなく、其の高さが、外側が高く、内側が低く、実際は逆のところが多いのみならず、堀之内が広大過ぎる。決して館址などではない。堀之内のなんたるかは、「堀之内の研究」を参照せられたい。石戸左衛門尉なる人は,鎌倉初頭東鑑に出てくる人物である。○東光寺境内の、桜樹の松元に、数多の石碑が喰ひ込まれて、林立する有様は、蓋し海内稀有の遺跡で
ある。此等の石碑は、銘丈から推して、当初から桜樹の根元に、建立されたものではなく、阿弥陀堂が建立された時か、叉は何時の頃か、此処へ寄せられたものである。
瀧澤馬琴の玄同放言に、樹下十五基とあるが、今二十余基ある。然し喰ひ込まれた十五基以外のもの
も、其銘丈から決して他村のものではなく、何れも曲輪内のものが、此処に再度集められたものであ
る。
以下覚束ない乍ら、ありし日の曲輪を、銘文から研究して見る事とする。

○最も古い貞永二年のものが、世に板碑の始源的のものとして、国宝に指定されて居るものである。貞
永二年は、嘉永元年から五十年、承久之乱から十年、鎌倉幕府の盛んな時である。其板碑には
光明遍照、十方世界,念佛衆生、攝取不捨
と、光明真言の一句が刻まれて居る。当事者会に碑のない折柄、石に刻した此教文が、如何に曲輪の
人を随喜せしめたかは、想像に余りある。と共に、早くも曲輪の人々が、浄土希求に悶えたかを、推する事が出来る。○次ぎは寛元々年のもの(貞永一軍から十年)である。
十悪五逆、臨経苦逼、敬称十念、花開金色、
十悪五逆を重ねて、臨終の苦逼るも、敬んで十念を信唱すれば、極楽往生は疑ひないの謂であらう。
十悪五逆と言ひ、ロン中苦逼と云。娑碆の惨たらしい業体を、彷彿せしめ、之れが生業とは言ひ乍ら、
生殺與奪の権を擅にした、因果の苦悩が、まざまざ見える心地がする。

○越えて四年、寛元四年三月、弥陀三尊の碑が建てられた。其銘に
卓乎池上、一丈六像、変現大小、更無定相、
と刻された。
教文の意義が、尠しく分らないが、此地の四周が水田で、当時に於ては、池沼と思はれるので、そこで卓乎として池の上に、そそり立つ弥陀三尊も、丈六の来阿弥陀如来も、更に変らないと、弥陀の浄土を希求し、教へられたものであらうか。乃ち此板碑が、後の阿弥陀堂建立の、先駆をなしたものであらう。○次ぎは文応元年六月(寛元四年から十五年)の碑で、
過去大輔公、尊霊、出離生死、往生極楽
とある。大輔公とは如何なる人か、分らないが、過去大輔公の供養に建立されたもので、過去とあるから、早く故人となった人で、其の人が、何年経っても、往生出来ず、迷ふて居るらしく、其為め追善供養したものであらう。
会津の郊外の刑場に(今は畑となり、松の木が一本立つて居る)、鎌倉在年銘のものであり、来迎弥陀三尊の、雲の上から光明を放つ御姿の、実に立派な大石像に、
右志者、為於此所、断罪聖霊、出離生死、往生極楽云々
の銘がある。それと軌を同うするもので、大輔公なる人は、恐らく此地に断罪された人であらうと思ふ。

○次ぎは同年七月のもので、覚厳大法師の為めに建立された。
覚厳大法師、往生極楽、証大菩提也
願主▢▢文応元年大才庚申七月
とある。この覚厳大法師も、如何なる人か分らないが、この人は、大輔公と違ひ、曲輪の人であらうと思ふ。
当時上方に於ては、曲輪の人を、内外共に、何々法師と呼んで居り、淡路法師とか攝津法師、吉野法師、播摩法師と古記録に出て来るので、真の僧侶ではあるまじく、大法師とあるので、名だたる頭だったのではあるまいか。
願主が孝子か、否か分らないが、特に消してあるので、此方は間違ひなく曲輪の人であり。覚厳大法
師の極楽往生疑ひない、大法要をしたときの建立である。
願主名を消したのは、元より近世の仕わざで、この例は実實に多い。比々然りである。願主の名があっ
ては、素性が分かる。かくては蒲の冠者の故事を、作る事も出来ない。そこで取って仕舞ふのであるが惜しい事がある。

○次ぎに文永年のものであるが、桜の中へ喰ひ込むで、上部種子丈しか見へない。将来桜が枯れて掘り出す時が來たら、往時を語る文字が、あるかも知れない。
○次ぎは弘安元年のもので
諸教所讃、多在弥陀,故以西方、而為一住
頗る落ち附いた銘文である。文字通り、西方を墓場とし、そこに建てられたものであらう。
他に弘安二年、延慶元年、文和三年、建武四年、延丈六年、貞治七年とあるが、断片が多く、銘丈も
見えない。其他不明断碑もある。○最後は永徳二年のもので、将軍は義満、室町幕府の盛んなときである。
設我得佛、十方衆生、至心信行、乃至十念、欲生我国、若不生者、不取正覚
右志者 為▢▢聖霊、往生極楽、証大菩提也
文応から百二十年、世相は草双子ものの流行を極め、地獄相の伝播で、罪の深いものの、末生は牛になるとか、馬になるとか、「霊異記」にある様な物語りが伝へられて、再び人間となれるか、なれないか、人々に苦悩のあった時代である。
牛か馬になる懸念の、大分あった聖霊に対し、大丈夫この大供養で、牛にも馬にもならないぞとて、建立されたものである。此の人も、其名を消して居るから、曲輪の人に間違ひない。


○以上で終りであるが、箱根蘆の関の人々が、浄土希求した通り、刑場を有した、鎌倉時代長吏の苦悩は、蓋し娑婆の人の想像以上のものであったと思ふ。
貞永は、今を距る事、丁度七百年、樺桜の見事さと言ひ、関東板碑の始源と言ひ、蓋しこの曲輪は、全国的に圧巻の、ものであらう。板碑の普及は、或は曲輪内の流行が、其先駆かも知れない。心ある人は、一度ば杖を引いて、弔ふべきであらう。○樺桜は、元より蒲の冠者に関係はない。範頼の伝説は、近世の作為である。桜の樹種が、方言樺桜と
呼ぶべきものである事を、土地の人が、忘れたものである。

○最後に曲輪が如何なる人によって、又如何なる郷によって設置せられたか、憶測を附記して他の参考とする。
鎌倉初頭、此地の地頭は、二人丈伝へられて居る。其一人は、石戸左衛門尉で、他は足立右馬允遠元である。
石戸左衛門尉は、東鑑に一人出る丈で、一族らしき人もなく、名族の人ではない様である。この人の館址を、一説に石戸宿に伝へられて居る。果して石戸宿に館址があったとすれば、同所は郡界近く、曲輪との配置が、逆になるから、其人と曲輪とは関係がない。
次ぎは足立方馬允遠元であるが、その館址を桶川宿であると伝へられて届る。遠元は頼朝が旗上げに際し、わざわざ隅田の陣屋へ呼んだ位であり、頼朝頼家二代、武芸の師範たりし人で、「丹波志」の記するところによれば、足立郡の領主であり、後郡の地頭職に補せられたとあり。子孫東鑑に、十余人其名が見えるから、鎌倉初頭の名族である。

北條氏になって丹波の国へ所領替へになったが、郡中此人の館祉を、他に伝へないのであるから、桶川説が真であるとしなければならない。
若し然りとすれば、畦吉は川越よりする入間街道を押へ、堀之内は、松山よりする比企街道を押へ、共に郡界に、地頭足立氏が配したかとなる。
若し地頭に関係ないとすれば、「和名抄」「稲直」の郷の所属となる。然し稲直の郷の本郷も、結局桶川宿に擬定さるべきであるから、この両曲輪は、桶川宿前身の配属と見て、大過ないのではあるまいか。
中世以降、この附近の治乱興亡は、途にこの曲輪には及ばなかった。寺は応永と、慶長と両度焼けたと言ふが、焼けずに残ったら、或は一節の文書位存在したかも知れない。文書は見込みないとしても、以上の板碑も、桜が抱き込まなければ、或は凡てが破棄されて居ったかも知れない。以て他の古き曲輪の往時を、類想すべきであらうか。


泥棒対策であろうか、神社の裏に回ろうとすると爆音でブザーが鳴ってびっくりした。


東光寺が時宗、墓地からも時宗と判断できる。高松という名字が多く、源範頼の家臣の末裔と伝えられるが、菊池山哉は「範頼の伝説は、近世の作為」としている。